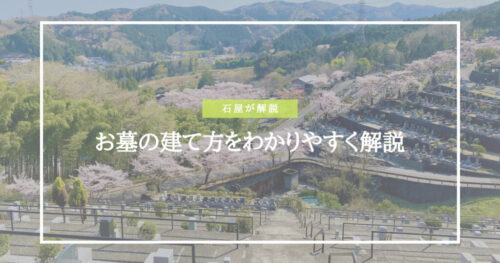- お墓を継いでくれる人がいない。
- お墓を準備したいけれど一般墓は高くて準備できない。
- お墓が遠くて管理が困難になっている。
今回はこういった悩みを解決するための方法として、一般墓を建てる以外の方法を解説していきます。
\永代供養墓を探したい方はこちら/
お墓を建てないで遺骨を供養する方法
結論を先に言ってしまうと、お墓を建てないで供養する方法として以下の方法があります。
- 永代供養墓で合葬する(ほかの人と一緒に埋葬する)
- 散骨する
- 自宅で手元に置いておく「手元供養」
それではそれぞれ詳しく説明していきます。
永代供養墓とは? お墓を建てない埋葬方法のひとつ
永代供養墓とは墓地の管理者がお墓の維持、管理をしてくれるタイプのお墓です。
契約した期間(決められた期間や永代に渡り)供養や管理をしてくれます。
※ここで言う永代というのは墓地が存続する限りという意味でつかわれます。
永代供養墓には三つの条件がありそれを満たしているお墓を永代供養墓といいます。
- 墓地の管理者に永代に渡り管理、供養が受けられる。
- 継承者の有無が関係ない。
- 生前から申し込める
いろいろなタイプの永代供養墓があり、各霊園ごとに「合葬墓」「合祀墓」などの名称がついています。
少子高齢化が進み、お墓の継承者がいない問題の対策として需要が高まっています。
公営霊園の合葬式の墓地は宗旨・宗派は自由なのですが、いろいろな宗旨・宗派の方がいるため
特定の宗教的な供養は行われません。
永代供養墓のメリット・デメリット
永代供養墓にはメリットも多くありますがデメリットもあります。
メリット、デメリットをどちらも考慮して検討しましょう。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 霊園やお寺が存続する限り、 永代に渡り供養してもらえる 一般墓に比べ墓石を建てない分費用が安い 維持費(管理料)などがかからない墓地も多い お墓の継承者がいなくても契約できる | 一度合祀されると遺骨を取りだすことが できない 合祀(ほかの人と一緒に埋葬)される お供物に制限があったり、個別にお墓参りができない |
永代供養墓の種類【納骨堂・樹木葬・樹林葬・合葬墓】
納骨堂

遺骨を土に埋めずに収蔵する施設です。
お墓を建てないため比較的安価です。
※土地によっては高価な所もある。
仏壇式やロッカー式、機械式などいろいろなタイプがあります。
収蔵期間もさまざまで一定期間や永代などがあります。
樹木葬・樹林葬

樹木葬、樹林葬ではお墓の代わりに樹木をシンボルとして遺骨を埋葬します。
費用も比較的安価で自然に還ることができる埋葬方法で最近人気が出ています。
ほかの人と一緒に埋葬する合葬タイプや家族でスペースを使えるもの、ネームプレートを設置できるなど様々なタイプがあります。
一度埋葬すると取り出せなくなる(改葬できない)場合が多いというデメリットがあります。
合葬墓・納骨塔

石材でできたモニュメントをシンボルとした永代供養墓です。
骨壺のまま納骨するタイプやほかの人と一緒に合葬するタイプなど様々です。
霊園によって合葬墓、合祀墓、共同墓などいろいろな名称で呼ばれています。
永代供養墓の費用
永代供養墓の費用についてそれぞれ見ていきます。
納骨堂の費用
| 霊園名 | 広さ | 収蔵期間 | 使用料 | 年間管理費 |
| 多摩霊園 (公営墓地) | 二体用 | 30年 | 22万7千円 | 3140円 |
| 八柱霊園 (民間墓地) | 二体用 | 20年 | 26万円 | なし |
| 赤坂浄苑 (民間墓地) | ※二体用 | 永代使用 | 150万円 | 1万8千円 |
樹木葬・樹林葬の費用
| 霊園名 | 埋葬方法 | 使用料 | その他 |
| 小平霊園 (公営霊園) | 樹木の下に合葬 | 12万8千円 | |
| 樹木の周辺に個別で埋葬 | 18万8千円 | ||
| 奥多摩霊園 (民間霊園) | 家族や親族とともに埋葬 | 52万円 | 環境保護費11万円 納骨料2万7500円 |
| 酒々井霊園 (民間霊園) | 個別で埋葬 | 20万円 | 永代管理料2万円 納骨料3万1900円 彫刻料5万5000円 |
| 合葬 | 10万円 | 永代管理料1万円 納骨料3万1900円 彫刻料2万2000円 |
霊園によりかかる費用、そのほかにかかる管理料などが変わるため確認しましょう。
\ 全国の永代供養墓を見てみる方はこちら/
【散骨】遺骨を海や山にまく供養
遺骨をパウダー状に砕き海や山にまく供養です。
故人の思い入れが強かった場所にまいてあげたい、お墓を建てる費用は高くて出せない、
お墓を継ぐ人がいないなどの理由で散骨を希望する人が一定数います。
散骨には法律の具体的な決まりがないため節度、ルールを守った散骨をする必要があります。
散骨のルール
散骨を行う際には必要最低限のルールを守る必要があります。
- 親族の了解を得る
- 遺骨を細かく砕き粉末状の遺灰にする。
- 自治体のルールを確認する。
- 散骨を行う場所を見極める
- 地主の承諾を得る
- 自然環境に配慮する
散骨を行うために
散骨を行うのに特に届出等は必要ありません。
しかしルール、配慮など素人では難しいためプロにお願いするのが一般的です。
散骨を希望する方はこちらからプロに相談してみましょう。
\散骨の相談はこちら/
手元供養
遺骨を自宅で保管し供養することを手元供養と言います。
遺骨を自宅で保管、供養することは禁止されていないので問題ありません。
自宅供養を選ばれる方の理由として
- まだ故人と離れたくない
- 見守っててもらいたい
- お墓が遠くてお参りに行けないため
といった理由が挙げられます。
手元供養する際には小さい骨壺に入れて保管する、
アクセサリーにする。 プレートなどに加工する方法があります。
まとめ
お墓を建てない供養の方法として
永代供養墓で合葬する(ほかの人と一緒に埋葬する)
散骨する
自宅で手元に置いておく「手元供養」
以上の方法があります。
お墓を建てることも含め、自分の思いにあう供養の方法を選択しましょう。
\ 永代供養墓を探す /